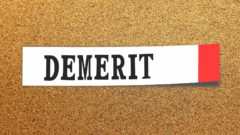みなさんこんばんは、マリアです。
このブログは月曜の19:00に公開できるよう予約投稿しましたので、恐らく今ごろの私は社会調査の期末テストがようやく終わって一息ついたのもつかの間、次の期末の提出課題の作成に追われている事でしょう。
日本は6月に入りましたが、お天気はどうでしょうか。
今週から下り坂に入りますという週間天気予報を見たのですが。
くれぐれも体調管理には気を付けて、楽しい一日を過ごしてくださいね。
それでは、今日のブログ、子供を取り巻く環境の話をしていきましょう。
私の専攻分野について
私は台湾の大学で児童心理学など学んでいます。
もともと発達心理学、脳科学、心理学に興味があったので心理学部と発達心理学部が学べる学部を受けたら、こちらに入学が決まりました。
我が校のここ数年の傾向を見ると心理学部の外国人枠は毎年中国語も英語も日常会話で使っているであろうマレーシア人に奪われています。
私が書類申請した年もマレーシア人に負けました、、、、、、。
そういう訳で幼児教育を学んでいるのですが、こどもの観察授業という科目があって金曜の夜に近所のイケアに行きました。
昼間暑かったので疲れてしまい、変な時間に寝てしまったのでお店に着いたら20:30でした。ここは一階にレジがあって、そこを出てきた所でソフトクリームやホットドッグなどが買えます。
店内に入ると20:30だというのに、抱っこしないと連れて歩けない赤ん坊や、幼稚園、小学生の子供連れの親御さんが何組もいました。
ここにはあまり席がないので3階に移動すると、子供が遊べるコーナーやレストレンがありました。ここにも子供がちらほらといました。
日本イケアと台湾イケア営業時間の違い
みなさん、日本のイケアは何時まで開いているか知っていますか?
公式サイトを見ると下記のようになっています。
月 ~ 金:10:00~21:00
土・日・祝日:9:00~21:00
では、台湾イケアはいったい何時まで開いているのでしょうか?
まずは台北にあるIKEA敦北店から見てみましょう。
IKEA敦北店
日曜~木曜及び国民の休日 10:00 – 21:30
金曜~土曜及び国民の休日の前日 10:00 – 22:00
次に新北市にあるイケアのうち我が大学に近い店舗を見てみましょう。
IKEA新莊店
月曜~日曜 10.00 – 22.00
最初はレストランで食事をしながら子供を観察していたのですが、21:00を過ぎたあたりから人がまばらになり、ドリンクコーナーのあたりは清掃を始め出したので、一階に移動しました。
ここのイケアには前からよく来ていたのですが、今までは自分の買いたいものや食べたいものばかり見ていました。店内のお客さんは大人か、学生でも大学生以上が多いと思っていたのですが、一階で座っていると、次から次へと子ども連れの親御さんがレジの方向から出てくる、出てくる。
そしてほとんどの親子連れがソフトクリームを買いに並びます。
閉店時間22時となっていますが、23:30ぐらいまで結構まだ人がいました。
子供たちの年齢層は入店時と同じ、赤ん坊、幼稚園児、小学生達連れが多かったです。
ソフトクリームを食べながら地下駐車場へ行くエレベータに乗る姿も見かけましたので、車に乗って親子連れで買い物に来ていた人も多かったようです。
子供たちはあまり眠そうな感じもなく、ご両親も買い物終わったら早く家に帰らなきゃという慌ただしい雰囲気もほとんど見かけませんでした。
子供たちがソフトクリームを買ったら、お母さんと三人で食品コーナーをのんびりと回りながら食べているというケースが多かった気がします。
このすぐ近くにフランスから来た大型スーパーのカルフールもあります。
カルフールを知ってますか
じつは私、日本にいた頃はイケアもコストコも、カルフールも行った事ありませんでした。
住宅密集地なので大型スーパーがないんです。
なのでジャスコとか、そういうのも日本の実家近くにはありません。
カルフールが日本にも入ってきたのは知っていたのですが、一度も行く事なく日本からすぐ撤退してしまったようです。
私は先に書いた三社ともすべて台湾に来てからはじめて行きました。
カルフールはイケアと比べるともう少しお手頃な品物が多く、食料品から家具まですべてそろうのでとても便利で気に入っています。そして台湾での店舗数がとにかく多いのです。
カルフールは店舗にもよりますが、台北市は小南門駅近くにある桂林店は大型スーパーなのにも関わらず24時間営業です。
新北市の他店舗の営業時間はほとんどが9:00~23:00、または9:00~24:00のどちらかで、遅くまで開いている事がわかります。
先ほどのIKEA新莊店から歩いて2分ぐらいの所にカルフール 重新店あるのですが、ここは金曜日は24:00まで開いています。
お店へ行くとさすがに人は少なかったですが、小学生や幼稚園の子供さんを連れた親御さんが2組ほどお会計を済ませてひと休みしている所でした。
以上のイケアやカルフールの例を見てもわかるように、台湾では共働きが多いので遅くまで開いているお店が多く、小さな子供連れで行く家族がいるのではないかと思いました。
そういえば前の記事にも書きましたが、台湾では病院も遅くまで開いているんですよね。
台湾の子供を取り巻く環境
台湾では「子供をこんな所に連れて来るなんて」という言葉をまだ一度も聞いたことがありません。
どういう経緯かわかりませんが、会社のオフィスや大学構内に自分のお子さんを連れてきている人に時々遭遇します。
あの子たちが親御さんと一緒にバスで来たのか、電車で来たのか、車で来たのかはわかりませんが、「電車の中に子供を連れて来るな」とか、「職場に子供を連れて来るな」という人は、たぶんいないんじゃないでしょうか。
それとは別の話で、大学内に幼稚園があるのですが、見ていると登園時間はみなさんけっこうバラバラで、子供を連れて遅れて教室に入って行く親御さんがたくさんいます。
日本だと病的なぐらい協調性を大事にするので「あー、遅れちゃいけないんだ~!!」とかいじわるいう子供もいそうな気もしますが、ここ台湾では幼稚園生のうちは遅れて来ることは何の問題もない事のようで、誰かが特に何か言っているのをまだ耳にしたことがありません。
大人顔負けで働く台湾の子供たち
台湾に住んでいると、朝市や夜市、商店などでお店を手伝っている子供たちがいる事に気づきます。
子供達はオーナーのお子さんか、お孫さん、親戚のお子さんという事がほとんどです。
小学生の頃なんて遊びたい盛りでしょうに、朝9時ぐらいにお店に行くと子供たちはテキパキと働いているのです。
家に一人で留守番させとく訳にもいかないからなのか、本人が手伝いたいというからなのか、理由はわかりませんが、子供たちは注文からお会計まで大人顔負けの仕事をします。
私が前に気に入ってよく行っていた朝ごはん屋さんは、食後にお会計をします。
お店には調理をするお母さんの他におじさん2人、おばさん1人、小学生のお嬢さん一人がいます。
私は毎回違うものを注文するし、紙にメモする訳でもないのに、彼女はいつも記憶力が良くてお会計をお願いすると、さっと料金を答えます。その姿はおじさんの店員さんが舌を巻くほどです。それにいつも愛想が良くて可愛らしいのです。
子供も大人も一緒に行動するのが台湾流
今回、イケアやカルフールに夜遅くまで小さい子供を連れて歩く親御さんの姿を見る事が出来ました。
私の台北や新北に住んでいるお友達は、結婚して独立するまでは、家族は一緒に住み、いくつになっても週末になると家族みんなで出かけている人が多いようです。
もう働いているお友達も多いので、彼彼女らは、お友達や会社の同僚、恋人などと遊びに行く事ももちろんあるのですが、それと同じぐらい家族みんなで出かける時間も多いように思います。
我が校の教授がいった衝撃のひと言
私が大学一年の時、ひとりの教授が授業でこんな話を生徒の前でしました。
「私の友人家族が、日本へ子供を留学させるために行こうと思ったんだけど、日本は子供に優しくない社会だと聞いて、アメリカに行きました」
確か、もう少し前後の説明があったと思うのですが、その時は「は?なにを言ってるの?失礼ね!」と思ったので、この部分しか記憶に残っていません。
それからネットでいろいろ調べ物をしていると「どこそこで子どもが騒いでいた。うるさい」とか、「子どもをこんな場所に連れて来るなんて!」といった書き込みがよく目に入るようになり、教授の言っていた意味がわかりました。
台湾と日本ではいろいろと違う部分も多いので、一概に何がどうと比べられないのですが、子供を取り巻く環境といった方面から見ると、子供にとって住みやすいのは台湾の方かも知れません。
日本は特にリーマンショック以降、国民の生涯雇用という概念が薄れ、その結果共働きの家庭が増えているようです。
そうなると子供さんがいるご家庭では、お子さんだけでお留守番させるわけにも行きませんから、時と場合によっては職場に連れて行ったりする事もあると思うのです。
それにお子さんが小さいうちは、時には幼稚園や保育園に遅れていく事があるかも知れません。
お父さん、お母さんだって、出来ればお子さんに「早くしなさい!遅刻しちゃうでしょ!!」とは言いたくないですよね。
長い人生、子供の送り迎えだけでなく、高齢者を抱えているご家庭では、仕方なく職場に遅れて行かなければならない時もある事でしょう。
台湾の人たちがなぜ、あまり急いだり慌てたりしないように見えるのか、まだ自分の中で解明できているわけではありませんが、何かあっても相手に対して沒關係と一言で済ませてしまう(「だいじょうぶ~」「気にしないで~」という、意味で使います)その性格に秘密があるような気がしています。
最近は沒關係を沖縄の人の「なんくるないさ~」と似ているなあと思う事が多いのですが。
期末の制作物を通して、今回本当にいろいろな事に気づかされました。
社会は前の世代から脈々と受け継がれるものであり、子供が幼いうちは大人たちが見守り、支えます。大人が老いて働けなくなった時には、その時の子供たちに支えてもらっています。
彼らが大人になったら今度はまたその世代の子供たちを彼らが支え見守り......と、それが世の中のしくみであり、誰もが通る道です。
日本の子供を取り巻く環境がもっと優しくなって、お互いにもっと「だいじょうぶ~」「気にしないで~」と言い合える世の中になったらいいなと思いました。
関連記事